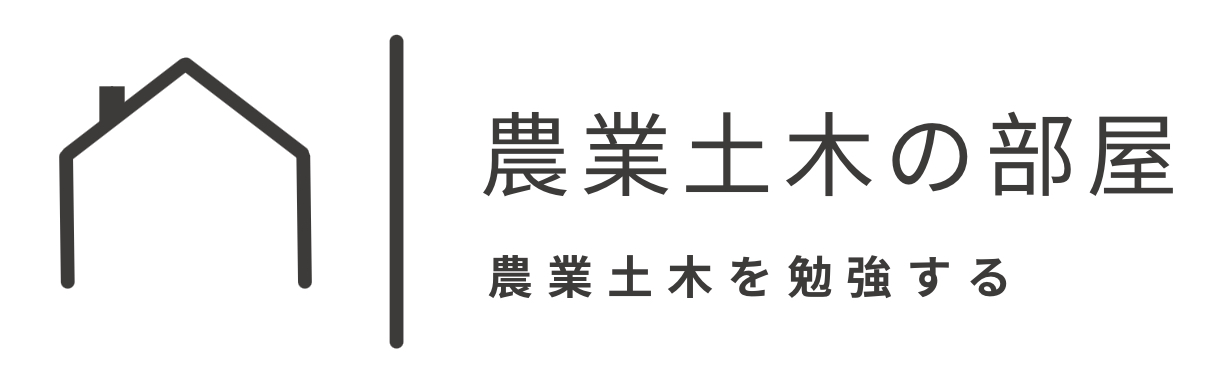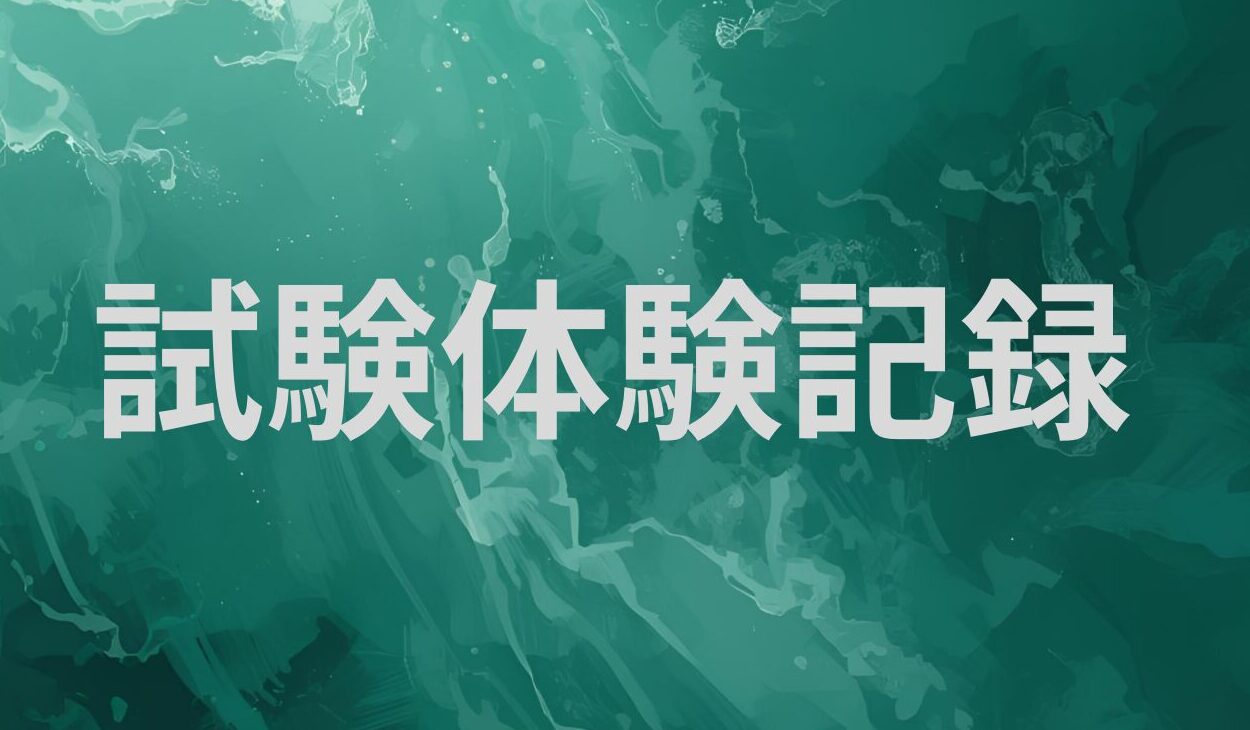こんにちは!
「農業土木の部屋」のノゴーンです。
2025年5月18日に測量士補試験に一発合格しましたので、勉強方法や試験対策から試験を通しての感想等をまとめていきます。
試験概要
令和7年度の試験について
資格試験名
測量士補試験
受験資格
年齢、性別、学歴、実務経験などに関係なく受験できる
試験方法
筆記試験(マークシートによる五肢選択)
試験日時
年1回(例年5月の第3日曜日)→2025年は5月18日(日)13:30〜16:30
受験費用
試験手数料は2,850円(収入印紙による書面受付)
試験の内容
試験科目
- 測量に関する法規
- 多角測量
- 汎地球測位システム測量
- 水準測量
- 地形測量
- 写真測量
- 地図編集
- 応用測量
問題数
28問
試験時間
3時間
試験の特徴
この試験の一番の特徴それは、決まった分野の問題が毎年出題されることです。
過去数年間の問題の類似問題が出題されます。
例えるとすれば1人のピッチャーが配球を変えて攻めてくる感じです。
持っている変化球は変わらないので、対策は非常にしやすいです。
つまり過去問をできるだけ多く解くことが合格への近道です。
(ただし、新問題が毎年数問だけ出題されるので、過去問で23問くらいは正解できるレベルにしておくことで、新問題が出ても高確率で合格点を取れるでしょう。)
合格基準
1問当たり25点。
700点満点。
450点以上(18問正答)で合格。
合格発表日
例年は7月となっています。
令和7年度は6月26日でした。
令和7年度合格率
51.2%(合格者数6,837人/受験者数13,363人)
難易度
例年の合格率は平均20〜40%となっています。
令和7年度に限定すれば2人に1人が合格していますので、比較的合格しやすい試験と言えるでしょう。
具体的な勉強方法
勉強前の状態
高校、大学で測量に関する授業・講義等の座学は受けたことがありません。
現在の会社に入社してから、簡易的な測量をしたことが数回ある程度でした。
つまり、前知識はあまりない状態です。
試験前の状態
以下で紹介する勉強をして、「これは合格できる!」とかなりの自信を持って臨みました。
試験の得点(自己採点)
私の得点は25点でした。
内訳は以下の表をご覧ください。
| 科目 | 問題 | 出題の趣旨 | 私の正誤 |
| 測量法規 | No.1 | 測量法 | ○ |
| No.2 | 公共測量における現地作業 | ○ | |
| No.3 | 測量に必要な数学 | ○ | |
| No.4 | 地球の形状と位置の基準 | ○ | |
| 多角測量 | No.5 | トータルステーションによる基準点測量 | ○ |
| No.6 | 基準点成果表 | ○ | |
| No.7 | 方向角の計算と水平角の閉合差 | ○ | |
| 汎地球測位システム測量 | No.8 | 基線解析・計算 | ○ |
| No.9 | 基線解析 | ○ | |
| 水準測量 | No.10 | 楕円補正 | ○ |
| No.11 | 観測誤差と消去法/視準線誤差・標尺の零点誤差 | ○ | |
| No.12 | 標尺補正 | ○ | |
| 地形測量 | No.13 | TSによる地形測量(等高線測量) | ○ |
| No.14 | 現地測量 | ○ | |
| No.15 | 地上レーザ測量 | ○ | |
| 写真測量 | No.16 | 撮影高度と縮尺の関係 | ○ |
| No.17 | 撮影高度と縮尺の関係 | ○ | |
| No.18 | 航空レーザ測深測量 | ○ | |
| No.19 | UAVレーザ測量 | ○ | |
| No.20 | 車載写真レーザ測量 | ✖️ | |
| 地図編集 | No.21 | 地形図の読図法 | ○ |
| No.22 | 平面直角座標系とUTM図法 | ✖️ | |
| No.23 | 地図編集の描画順序 | ○ | |
| No.24 | GIS(地理情報システム) | ○ | |
| 応用測量 | No.25 | 路線測量(作業工程) | ○ |
| No.26 | 路線測量(障害物がある場合の曲線設定) | ○ | |
| No.27 | 用地測量(面積計算) | ○ | |
| No.28 | 河川測量(作業工程) | ○ |
使用教材
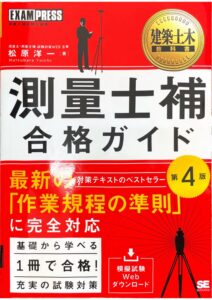
使用させていただいたのは、松原洋一さん著「測量士補合格ガイド」です。
こちらの教材を選んでよかったと思えるポイントは、初学者にもわかりやすいように基礎編と応用編を分けて構成している点です。
また、過去問の攻略が鍵となる本試験において、過去20年以上の測量士補試験に出題された内容を項目別に分類して、解説、例題、本試験問題とステップを踏んで理解できるように配慮されている点も受験生にとっては大きなポイントでしょう。
各設問に対して図解を交えながらの教材となっているため、塾やオンライン講義のような対人でなくてもわかりやすく学びを進めることができました。
合格までの勉強時間
私の部署では、年度末にかけて仕事が忙しくなるため、3月いっぱいは勉強時間が確保できませんでした。
4月になり、半ば合格を諦めていたところ、家族に発破をかけられ一転やる気になりました。
そこから勉強をスタートしました。
平日は仕事から帰ってきて、2時間程度勉強します。
土日は一日6時間くらいの勉強をしていました。
つまり、一週間あたり22時間(2×5+6×2)をして、4月から試験日まで7週間あったので、156時間(22×7)程度の勉強時間を確保していました。
勉強期間はそこまで長くはありませんでしたが、短期集中で効率的に理解を深めていった結果、合格に繋げられたのかなと思います。
合格に向けて意識したこと
とにかく「過去問を解いて、わからない点を潰していく」ことに重点を置いて勉強を進めました。
毎年類似問題が出題されるので、過去問を軸に勉強しましょう。
具体的には、まず全くと言っていいほど測量士補で使える知識がない状態だったので、先ほど紹介した参考書を一周しました。
この時、参考書の中にある問題も解いていきます。
わからなくてもそのまま進みます。
ただし、理解できなかった問題にはチェックを入れておきましょう。
参考書を一周したら、ここからは過去問に取り組みましょう。
過去問を解くときに、時間は測る必要はありません。
一問一問理解するまで進みましょう。
どうしても理解できない問題は飛ばしても構いません。
なぜなら、28問中18問正解すればいいからです。
10問は間違えられるので、絶対に全て理解する必要はないのです。
ですが、なるべく捨て問題は作らないほうがいいので、ここでも理解できなかった問題にはチェックをしておきましょう。
そうやって一つずつ理解できるように丁寧に進んでいき、2〜3年分の過去問を解いてくると、ある程度正解まで辿り着ける問題が増えていることに気が付きます。
ある程度、自信を持って解けるようになった問題がわかるようになるでしょう。
そのあたりから時間を測ってみるといいでしょう。
時間を測ってみて、自信を持って解答して正解していた問題に関してはもう解説をじっくり読むことはしなくていいでしょう。
やっぱりわからなかった、もう少しで正解だったのに、という問題を理解することに時間を使ってください。
毎年試験に出てくる分野は同じなので、1年に数問ずつ解ける問題を繰り返していけば、5〜6年分といた頃には合格点は超えていけるでしょう。
勉強方法で改善したいと思ったこと
試験対策期間は7週間となり2ヶ月未満となりましたが、本当はもっと反復して知識を定着させるために、長めに勉強期間を確保できればよかったなと思います。
試験直前にやったこと
試験直前で、これまで理解できなかった計算等の考え方を新たに理解しようとしても、そんな時間はありません。
そこで私が試験直前に見ていたのは地図編集の分野の地形図の読図です。
これは、問題のキーワードで出てきている地図記号がわからないと解答までたどり着けない問題です。
逆にいうと、地図記号がわかれば、それをヒントにして正答まで辿り着くのは難しくない問題です。
地図記号はギリギリまで見つめて一つでも多くの地図記号を覚えるようにしましょう。
おすすめの学習アイテム・ポイント
私はよくいるタイプで、家では私生活と勉強の切り替えが難しく、誘惑に負け、勉強が手につきません。
そこで休日は図書館の自習室、カフェに行っていました。
時には平日の夜もカフェに行く日もありました。
図書館やカフェは周りに同じような勉強している人やサラリーマンが作業をしていたりして刺激を受けやすい環境にあります。
それに影響され頑張れました。
次におすすめなのはユーチューブで解説動画を見たことです。
ありがたいことにユーチューブで測量士補試験に関する解説をしてくださっている方や、単純に測量の知識を解説していらっしゃる方がいます。
文字と図解だけではわからない問題がある方には本当におすすめです。
ぜひ活用させていただきましょう。
試験の感想
過去問からの出題がほとんどというのは令和7年度も同じでした。
難易度はそこまで高くはないと感じたので、諦めずに取り組んでよかったと思います。
やはり過去問を繰り返し解けば間違いなく合格できる試験だと思いました。
これから受験する方へ
測量士補試験は間に合わないと思っても一つずつ課題を潰していけば必ず合格できる試験です。
自分を信じて、勉強していきましょう。
まとめ
測量士補試験は比較的難易度は低めで対策がしやすい試験です。
ただし、油断していると足元をすくわれて不合格になる方も一定数います。
難易度は比較的低いとはいえ、試験が年間1回だけの開催というのが受験者を悩ませますよね。
しっかり対策すれば独学でも十分合格を目指せる試験ですので、一発で確実に合格を勝ち取れるように、十分な対策をして試験に臨みましょう。